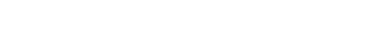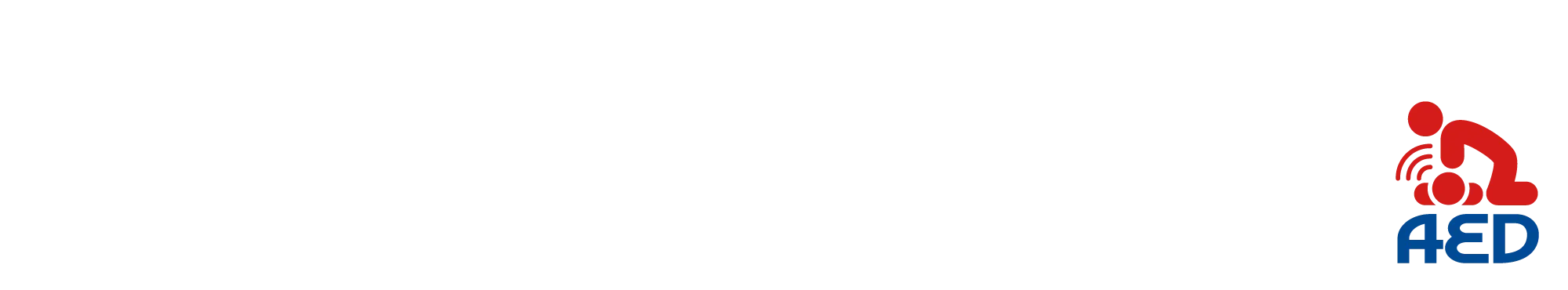

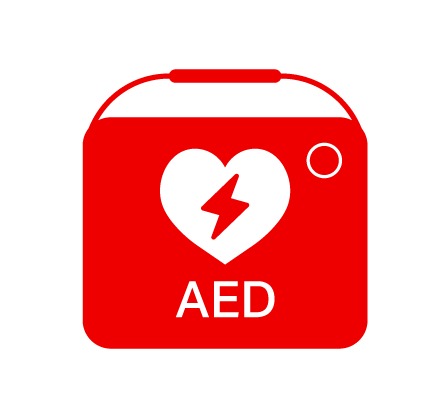
AEDとは?
AEDとは?
AED(自動体外式除細動器)は、心停止の際に心臓に電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。心停止が起こると、心臓は不規則な動きや細動を起こし、血液を全身に送り出すことができなくなります。AEDは、この状態を検知し、電気ショックを与えることで心臓のリズムを整え、再び正常に拍動させることを目的としています。
AEDは専門的な医療知識がなくても、誰でも使用できるように設計されており、音声ガイドに従って簡単に操作が可能です。緊急時には、適切な場所にパッドを貼り付けるだけで、AEDが自動的に心電図を解析し、ショックが必要かどうかを判断します。
AEDの普及率
近年、AEDの普及は世界中で進んでいますが、その普及率には地域ごとに大きな差があります。日本では、公共施設や駅、商業施設、学校などを中心に約60万台以上のAEDが設置されており、その数は年々増加しています。また、国内のAEDの設置率は世界でもトップクラスで、特に鉄道駅や空港、ショッピングモールなど、人が多く集まる場所での設置が進んでいます。
しかし、住宅や個人宅への普及率はまだ低いのが現状です。多くのAEDが公共の場に設置されているため、心停止が発生した場所によっては迅速に対応できない場合もあります。特に家庭内での心停止に対応するためには、家庭へのAED普及が重要です。心停止は家庭内で発生するケースも少なくないため、自宅にAEDがあれば迅速な対応が可能になり、救命率の向上につながります。
一方、海外の先進国でも公共施設への設置が進んでおり、例えばアメリカやヨーロッパ諸国では学校や企業、さらには地域コミュニティにAEDが普及しています。しかし、日本と同様に、家庭内への普及率はまだまだ低いのが現状です。
AEDと救命措置
心停止が起きたときに最も重要なのは、迅速な救命措置です。AEDと心肺蘇生法(CPR)は、救命措置において欠かせない2つの要素です。CPRは、心停止時に血液を循環させるための応急手段であり、AEDが到着するまでの間、心臓と脳への酸素供給を保つことができます。
AEDを使用することで、心停止の原因となる心室細動(VF)や無脈性心室頻拍(VT)といった不整脈を矯正し、心臓の正常なリズムを回復させることが可能です。AEDがショックを必要と判断した場合、自動的に電気ショックを指示します。また、使用者が戸惑わないように音声ガイドが操作をサポートしてくれます。
未就学児への適用
AEDは未就学児(1歳以上)にも使用できます。未就学児に使用する場合は、小学生~大人とは異なるモードや専用の未就学児用パッドを使用することが推奨されています。未就学児用パッドを使用することで、電気ショックの強度が自動的に調整され、小さな体にも安全に適用することができます。
また、乳幼児(1歳未満)の場合は、特別な注意が必要ですが、緊急時には医療機関に指示を仰ぎながら対応することが求められます。多くのAEDは、未就学児用と小学生~大人用の切り替えが簡単にできるようになっており、未就学児用パッドをセットするだけでモードが自動的に調整されます。